画面の中で、新総裁・高市早苗氏がこう語っていたのです。
「ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いてまいります。」
その一言を聞いた瞬間、胸の奥に小さな灯がともりました。
ここまで言って、今の日本のために本気で働いてくれるというのなら──
この先の日本は、少しは明るい未来になっていくのかもしれない。
そう思えたのです。
もちろん、不安もあります。
「働くこと」がここまで重く響く時代に、
また誰かが無理を重ねてしまうのではないかという心配も。
それでも、覚悟を言葉にできる人が現れたことに、
どこか希望を感じずにはいられませんでした。
──この国は、どこへ向かおうとしているのだろう。
そんな問いが、静かに私の中で芽を出しました。
高市早苗という人物──世襲ではなく、自らの努力で掴んだ道
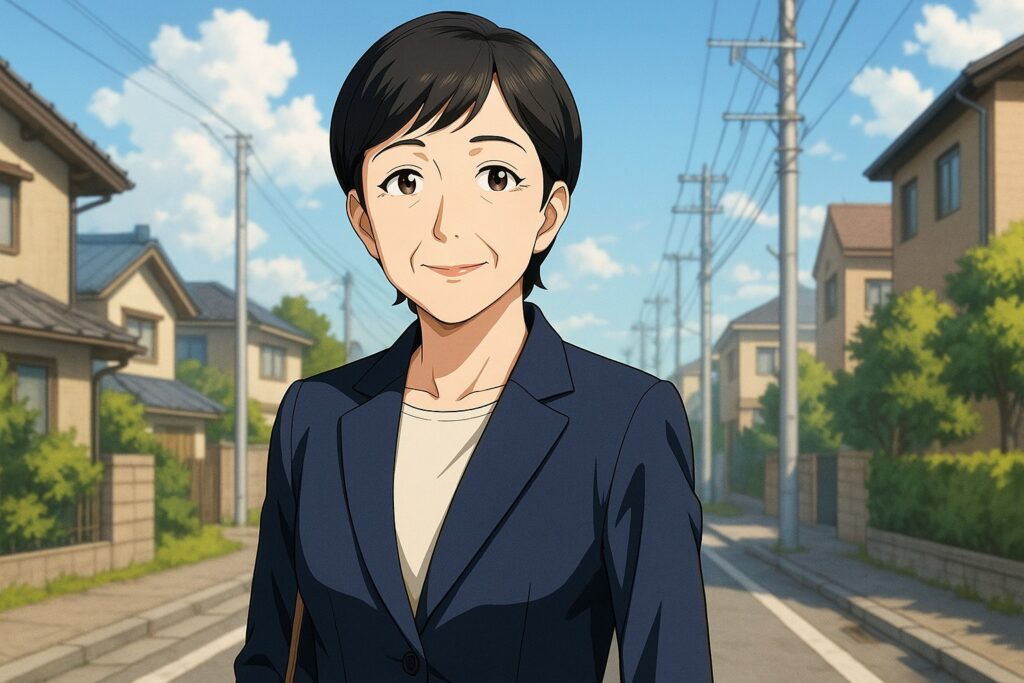
奈良で育った「普通の家庭の娘」
高市早苗さんは、1961年、奈良県で生まれました。
父は設備機械メーカー勤務、母は奈良県警で働く共働きの家庭。
決して裕福ではありませんでしたが、誠実に働く両親の背中を見て育ったといいます。
華やかな政治の世界とは無縁の、どこにでもある家庭。
けれど、そこから生まれた「努力すれば道は開ける」という信念が、
彼女の人生の根を支えてきたのだと思います。
「学費は自分で」──苦学の学生時代
高校卒業後、慶應義塾大学や早稲田大学にも合格していたものの、
家庭の方針で進学を断念。
「短大以上に行くなら学費は自分で出しなさい」という親の言葉に背中を押され、
神戸大学経営学部に進学しました。
昼は講義、夜はアルバイト。
学費も生活費も自分の力で賄いながら勉学に励んだ学生時代。
ときには深夜まで働き、眠い目をこすりながら翌朝の講義に向かったといいます。
そんな日々の中でも、彼女は軽音楽部に所属し、ドラムを叩いていたそうです。
硬い印象の裏にある、意外な“情熱”の部分。
そのリズム感こそ、後の彼女の政治的スタンス──
「現実のリズムに合わせながらも、自分のテンポを崩さない」──につながっているのかもしれません。
報道と政治の現場で磨かれた“現実主義”
大学卒業後、NHKに入局し政治記者として活動。
取材を通じて出会った政治家たちの姿に、彼女は学びと同時に疑問を抱いたといいます。
理想だけでは動かない現実。
でも、現実だけを見ていては人の心は動かない。
その狭間で、彼女の中に「自分ならこうしたい」という思いが芽生えていきました。
やがて松下政経塾へ。
政治を志し、米国議会での政策調査も経験。
そこから帰国し、いよいよ政界へ足を踏み入れます。
誰の支援でもなく、自らの意志で。
高市早苗という政治家の“芯”は、まさにこの時に形づくられたのでしょう。
女性初の総裁として、歴史の扉を開く
そして2025年──。
高市さんは、日本で初めて女性として自民党総裁の座に就きました。
テレビの画面に映るその姿は、どこか誇らしく、そして少し切なくもありました。
彼女の信念は一貫しています。
「努力する人が報われる社会をつくりたい」。
それは今の時代には少し眩しすぎるほど真っ直ぐな言葉かもしれません。
けれど、その真っ直ぐさこそが、
疲れきったこの国に必要な“希望の種”なのだと思います。
もちろん、努力だけではどうにもならない現実もあります。
それでも──“努力する人が報われる”という信念を掲げる彼女の姿を見て、
私はほんの少し、前を向ける気がしました。
「ワークライフバランスを捨て働く」発言にSNSで賛否の声
発言の真意──「働いて国を立て直す」覚悟
自民党新総裁に就任した高市早苗さんは、会見でこう語りました。
「ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いてまいります。」
その瞬間、ネットはざわめきました。
“働く覚悟”を真っ向から掲げたこの言葉は、トレンド入りするほどの注目を集めたのです。
「時代に逆行している」「家庭や健康を軽視している」──そんな批判も多くありました。
けれど、それ以上に多かったのは“賛同”の声。
日本を本気で立て直そうとするリーダーを待ち望んでいた人たちの、切実な願いのようにも感じました。
賛同する声:「よく言った」「日本を変える原動力になる」
日刊スポーツによれば、X(旧Twitter)上では次のようなコメントが寄せられていました。
「よく言った」「この国を取り戻すためには必要な言葉だ」
「日本人は長く働いてきた民族。原点を取り戻そう」──
そんな投稿が並び、彼女の姿勢に共鳴する人が多く見られたといいます。
(日刊スポーツ)
「本気でやる人がようやく出てきた」
「信じてついていけるリーダーが現れた」──
そんなコメントも目立ちました。
疲弊した社会の中で、“責任を引き受ける覚悟”を見せた高市さんの姿に、
多くの人が久しぶりに希望を感じたのだと思います。
批判する声:「過労死社会に戻るのか」「家庭を犠牲にしないで」
一方で、SNSには慎重な声も数多く投稿されました。
「また“働きすぎ”が正義になるのか」
「家庭を犠牲にして成り立つ経済はもういらない」
「バランスを失えば、心が壊れる人が増える」──
その不安は、かつて同じように働きすぎて苦しんだ人たちの記憶でもあります。
私自身も、どちらの気持ちも分かる気がします。
誰かが国のために走ることは尊い。
けれど、誰かがその陰で倒れてしまうのなら、それは本当の“立て直し”とは言えません。
だからこそ、この発言を“命を削って働け”という号令ではなく、
“もう一度、みんなで立ち上がろう”という呼びかけとして受け取りたい。
彼女の言葉に感じたのは、悲しみではなく、
「今度こそ変わるかもしれない」という静かな希望でした。
外国人・難民政策をめぐる発言と反響
「お帰りを頂く」──物議を醸した発言
新総裁就任後のインタビューで、高市早苗さんは外国人・難民政策についてこう語りました。
「経済目的で難民を装って来られる方、この方々にはお帰りを頂く。」
この発言は、TBS系の報道番組でも取り上げられ、SNS上で瞬く間に話題となりました。
支持する人々からは「国を守るための現実的な判断」「日本の秩序を壊さないための勇気ある発言」という声が上がり、
一方で批判する人々は「人道的視点に欠ける」「外国人排斥の空気を助長する」と懸念を示しました。
(日刊スポーツ)
賛否のどちらも、きっと“本音”なのだと思います。
守りたいものが違えば、正しさの形も違う。
その揺れの中で、私たちは「誰を守りたいのか」という問いを突きつけられています。
「日本人が我慢している」──現場からの声
高市さんは同じインタビューの中で、
「日本人が我慢している状況は良くない」とも語りました。
地方で暮らす私たちにとって、その言葉には確かに実感があります。
近所のスーパーやコンビニ、介護施設でも外国人労働者を見かけることが増えました。
彼らは真面目に働き、社会を支えてくれています。
けれど同時に、「言葉が通じない」「文化が違う」といった小さなすれ違いが、
地域の不安として積み重なっていくのも事実です。
“我慢”という言葉が、今の日本ではどこか日常語になってしまいました。
我慢で支える社会は、長くは続かない。
その意味で高市さんの言葉は、単なる強硬発言ではなく、
“限界の声”に耳を傾けてほしいというメッセージにも聞こえました。
賛否の狭間にある、生活者の本音
外国人問題は、賛成か反対かで分けられるものではありません。
「多様性を受け入れたい」という思いと、
「暮らしが壊れてしまうのでは」という不安が、私たちの心の中に同時に存在しています。
だからこそ、政治がすべきことは、誰かを排除することではなく、
“共に生きるための道筋”を示すこと。
働く場所、住む場所、支える仕組み──それらを整えるのが政治の役割のはずです。
高市さんの「お帰りを頂く」という言葉は、
決して軽く聞き流せるものではありません。
けれどその奥にあるのは、“日本を守る”だけでなく、
“人が安心して生きられる社会をどう作るか”という問いなのだと思います。
そしてその問いは、国の問題であると同時に、
私たち一人ひとりの心の中にも投げかけられているのかもしれません。
生活者の視点から見る:物価・格差・外国人問題への期待と現実

上がり続ける物価と「見えない我慢」
スーパーのレジで、また少しだけ手が止まります。
卵1パックの値段、牛乳の値段、電気代の請求書──どれも少しずつ高くなっている。
「賃上げ率が上がった」とニュースで聞いても、地方で暮らす私たちには実感がありません。
高市総裁は「経済の立て直し」を最優先に掲げています。
けれど、私たちが本当に望むのは、数字ではなく“暮らしの実感”です。
家計簿の数字では測れない“心の余裕”こそ、いま最も欠けているものかもしれません。
レジの前で、ため息をつかずに買い物できる日。
それがどれほど幸せなことか──
そんな小さな日常を、もう一度取り戻せる社会になってほしいと願っています。
努力が報われない格差の連鎖
高市さんは「努力する人が報われる社会を」と語ります。
けれど、現実では“努力しても報われない人たち”が増えています。
働いても、働いても、生活は少しも楽にならない。
「子どもの習い事を減らした」「ボーナスが減って外食を我慢した」──
そんな会話が、近所のママ友との間で当たり前になってしまいました。
本当に必要なのは、“頑張れない人を責めない社会”なのだと思います。
頑張る人が報われるだけでなく、
倒れた人に手を差し伸べられる国であってほしい。
政治の理想と現実、その狭間で苦しむのは、いつだって私たち生活者です。
共に生きることの難しさ──外国人労働者と地方の現実
私の住む町でも、外国人労働者の姿が増えました。
スーパーのレジ、介護施設、建設現場。
どこに行っても、彼らが懸命に働いている姿があります。
一方で、「言葉が通じない」「文化が違って不安」といった声も耳にします。
その気持ちも分かります。
急に変わっていく地域の景色に、心が追いつかない人も多いのです。
高市さんの「お帰りを頂く」という言葉には、
賛否を超えて“現場の違和感”がにじんでいました。
でも、排除することは解決ではありません。
大切なのは、誰かを追い出すことではなく、
“共に暮らすための仕組み”を作ること。
人を分けるのではなく、支え合う方向に舵を切れるのなら──
きっとこの国は、もう少し優しくなれる気がします。
“努力”だけでは追いつかない社会で、私たちはどう生きるのか

頑張り続ける人ほど、壊れていく
「努力すれば報われる」──かつて日本を支えてきたこの言葉は、今や少し重たく響きます。
働き方が多様になったと言われながらも、現実では“止まることを許されない”人が増えています。
仕事に追われ、育児に追われ、介護に追われ、気づけば自分の時間がどこにもない。
そんな生活の中で、心だけが少しずつ疲れていくのです。
SNSでは、高市総裁の発言に「元気をもらった」「背中を押された」という声が多く見られました。
けれど同時に、「もう頑張りたくても頑張れない」「これ以上は無理」という声も、確かに存在します。
どちらの感情も、本音だと思います。
みんなそれぞれの場所で、限界のギリギリまで頑張っているのです。
「ワークライフバランスを捨てる」ことの危うさ
「バランスを捨てる」という言葉には、強い意志と同時に、どこか危うさも感じます。
家庭を守りながら働く女性にとって、“捨てる”という選択肢は現実的ではありません。
ワークもライフも、どちらも大切で、どちらも欠かすことはできない。
片方を切り捨てた瞬間、きっと心のどこかが壊れてしまう。
高市さんの言葉が「覚悟」から生まれたのだとしても、
社会がそれを“当然の義務”として受け取ってしまえば、
また同じように、誰かが静かに傷ついていく。
それだけは、繰り返してはいけないと感じます。
希望を繋ぐために──「支え合う社会」へ
いま私たちは、“努力する社会”から“支え合う社会”への分岐点に立っています。
自分だけが頑張るのではなく、誰かと頑張りを分け合う。
弱さを隠すのではなく、支え合う強さを持つ。
そんな優しさが、これからの日本に必要なのではないでしょうか。
高市総裁が「働いて国を立て直す」と語ったその先に、
「働く人を守る政治」が続いていくことを、私は願っています。
頑張ることを誇りに思いながらも、
同じだけ“休むこと”“支え合うこと”が尊重される社会へ──。
それが、未来を明るくする一歩になると信じています。
それでも信じたい。女性が立つこの国の新しい夜明けを
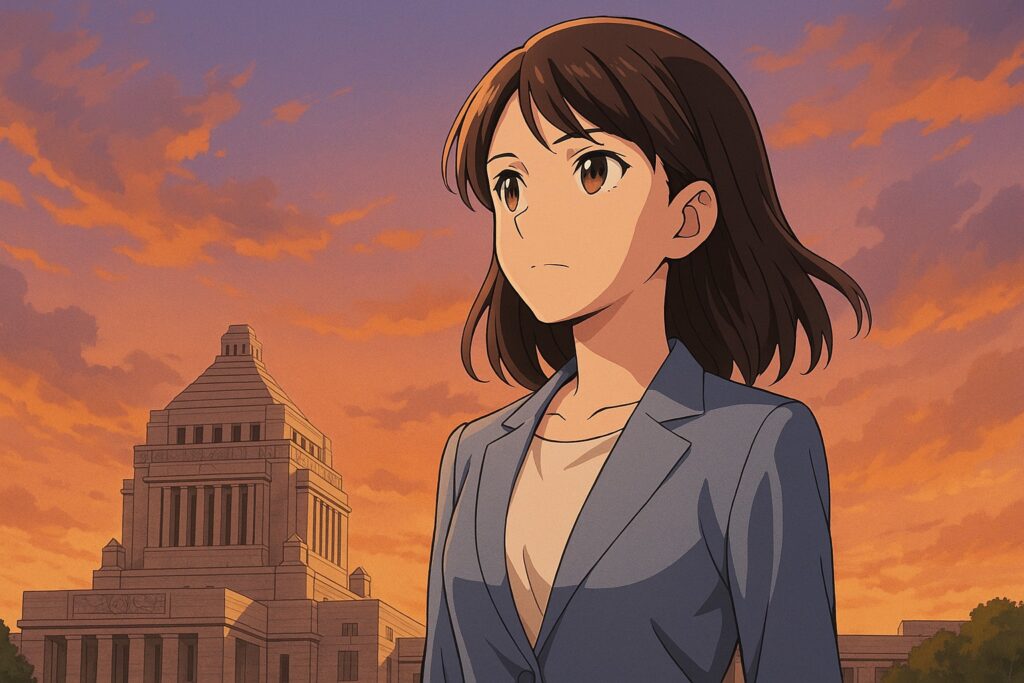
「女性初の総裁」が持つ意味
高市早苗さんが日本初の女性総裁として立った瞬間、
私はテレビの前で、思わず息を呑みました。
政治の中心に女性が立つ──それは、長い間「当たり前ではなかった光景」でした。
家庭と仕事の狭間で揺れながら生きてきた多くの女性にとって、
彼女の就任は“新しい時代の合図”のように感じられたと思います。
「女性が政治を動かす」──その言葉の響きに、
少しだけ未来への希望が差し込んだ気がしました。
「強さ」と「優しさ」のはざまで
ただ、女性だからこそ背負わなければならない重さもあります。
“優しくあるべき”と求められ、“強くあれ”と期待される。
その両方を同時に満たすことを、社会はいつの間にか当然のように女性に求めてきました。
高市総裁は「国を守る強さ」を前面に出す政治家です。
けれど、私はその強さの中に“誰かを守りたいという優しさ”があると信じています。
覚悟の裏側には、きっと祈りのような想いがある。
それこそが、女性のリーダーが持つ本当の力なのだと思います。
希望をつなぐ灯として
不安が消えたわけではありません。
けれど、政治の世界に女性の声が響き始めたこと──
それ自体が、この国にとって小さくも確かな一歩です。
誰かが道を切り拓かなければ、次の世代は変わらない。
その「誰か」が高市さんであることを、私は素直に誇りに思います。
彼女の一言ひとことが、光にも影にもなりうるからこそ、
私たち一人ひとりの受け止め方が未来を形づくっていくのだと思います。
母として、ひとりの女性として──
私はこれからも、小さな希望の灯を絶やさずに見つめ続けたい。
そしていつか、娘の世代がこの国の“夜明け”を当たり前に迎えられる日を、
心から願っています。
FAQ:高市早苗の政策で暮らしはどう変わる?
Q1. 高市早苗総裁の経済政策は?
高市総裁は、物価高や円安を背景に「経済の安定と安全保障を両立させる」方針を掲げています。
主な柱は、エネルギー・防衛・デジタル分野への国家投資。
特に「デジタル円」の導入や、戦略的な国内生産の強化を打ち出しています。
インフレを抑えるための金融政策にも言及しており、「物価の安定は国民生活の基盤」と強調しています。
Q2. 子育て支援策にはどんな内容がある?
子育て世代の支援としては、出産・教育費の減免や保育士の処遇改善などが検討されています。
また、女性の再就職やリスキリング支援にも力を入れる方針を示しています。
ただし、現時点では財源の明確化や実施時期は未定で、具体的な効果を実感できるかどうかは今後の課題です。
Q3. 外国人・難民政策はどう変わる?
高市総裁は、外国人労働者・難民問題に対し「現実的な線引きを設ける」姿勢を取っています。
経済目的での入国を厳しく取り締まる方針を示し、同時に真に保護が必要な人への支援を行うとしています。
この方針は「国を守る立場」としての評価がある一方で、「多様性を受け入れる社会」とのバランスに課題を残しています。
Q4. 地方に住む私たちの暮らしに影響はある?
高市さんは「地方創生」も重要なテーマに位置づけています。
企業の地方移転やリモートワーク推進を通じて、東京一極集中の是正を目指しています。
しかし、地方経済の基盤となる中小企業や農業支援の政策がどこまで実現されるかは、まだ不透明です。
Q5. 今後の政治姿勢で注目すべき点は?
防衛・経済・社会保障の三本柱を軸にしながらも、
「信念を貫く強さ」と「現場に寄り添う柔軟さ」をどう両立できるかが鍵になります。
初の女性総裁として、言葉だけでなく“暮らしの変化”として実感できる政治を期待したいところです。
まとめ:不安と希望、そのあいだで

「捨てる」という言葉が投げかけたもの
「ワークライフバランスを捨てる」──その言葉は、多くの人に衝撃を与えました。
けれど、そこには高市早苗総裁自身の“生き方”があるのだと思います。
努力で道を切り拓き、誰よりも働いてきた人だからこそ言える言葉。
それが希望として届く人もいれば、痛みとして響く人もいる。
どちらも正しく、どちらも、この国の現実です。
あの言葉は、私たちに問いを投げかけました。
──働くとは何か。
──支え合うとは何か。
その問いに、まだ誰もはっきりと答えを出せていません。
生活者として感じた「矛盾」と「共感」
私も、あの発言を聞いたとき胸がざわめきました。
頑張ることの大切さを知っている。けれど、頑張り続けることの苦しさも知っている。
「もうこれ以上は無理」と感じる日が、誰にでもあります。
だからこそ、高市さんの言葉に共感と戸惑い、両方の気持ちが入り混じりました。
努力を続ける強さと、立ち止まる勇気。
この二つのあいだで揺れながら、それでも前を向こうとしているのが、
今の日本の多くの人たちなのかもしれません。
それでも、未来を信じたい
高市総裁が日本初の女性リーダーとして立ったことは、間違いなく新しい一歩です。
その一歩が、“誰かを犠牲にした前進”ではなく、“誰かを支えながら進む未来”であってほしい。
働くことが誇りであり、同時に優しさにもつながる──
そんな社会を、私は心から願っています。
スーパーのレジで、私は今日も買い物をします。
手に取った卵の値段を見て、ほんの少しだけ息をつく。
けれど、心の中では小さく祈っています。
──どうかこの国が、「頑張ること」だけを強要しない場所になりますように。
そして、“支え合いながら生きる”ことを、もう一度誇れる時代になりますように。
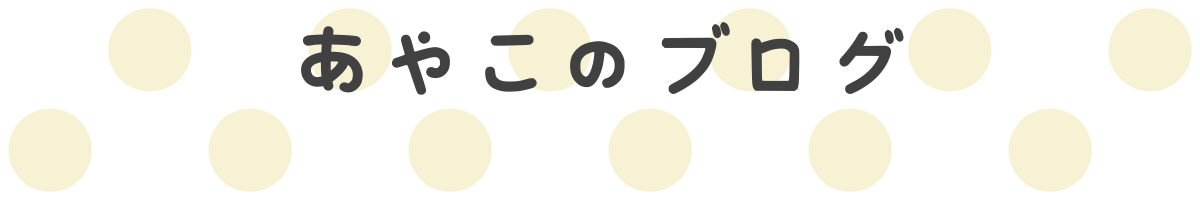
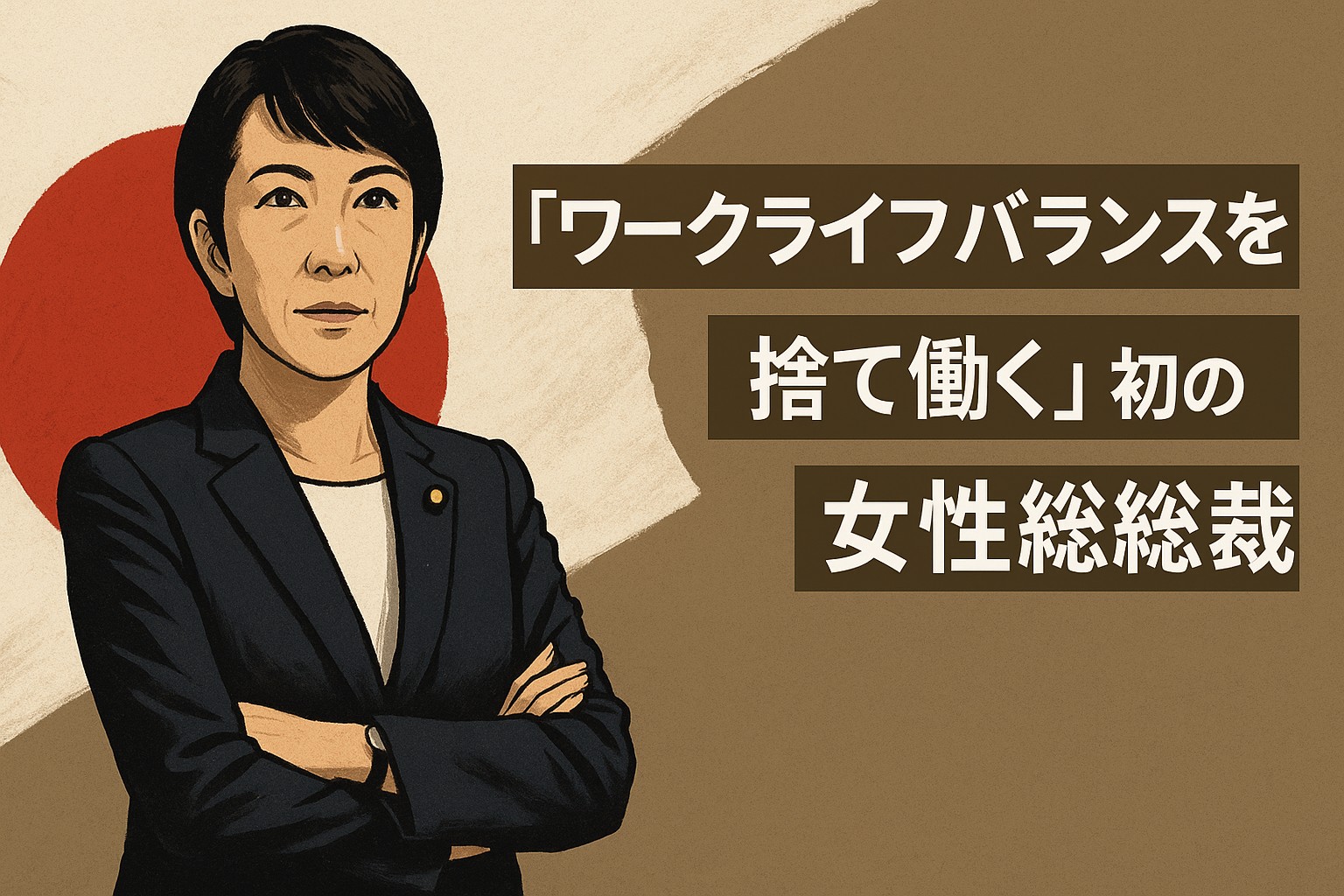


コメント